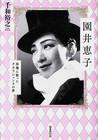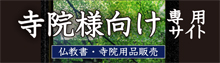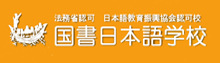★『園井恵子 原爆に散ったタカラジェンヌの夢』が原爆忌前後に広く話題になりました。
「北海道新聞」(8月13日付)、「西日本新聞」(8月26日付)などでは「さまざまな役を演じた際のブロマイドや日常の表情を写したアルバムなどを収録し、イメージをかきたてる書だ。演技の深淵に魅せられ、道を求めた俳優の姿が派優の姿がここによみがえる」(米田綱路さん)との評。
★『寝煙草の危険』が各紙誌で話題。
「読売新聞」(8月20日付)では「人生には何度か、読むことで自分が変わる本との出会いがある。読みながら自分が言葉で塗り変わっていく、書き換えられていくような、鳥肌立つ経験。ああ、出会ってしまった、という諦念にも似た気持ち」という池澤春菜さんの強い言葉が。
また作者マリアーナ・エンリケスさんとSF作家の倉田タカシさんとの対話が、「WIRED」50号に「SF的想像力とホラー的想像力について」と題して掲載されています。『寝煙草の危険』収録作「どこにあるの、心臓」については「ウィリアム・バロウズ、J・G・バラード、デヴィッド・クローネンバーグに影響されて書いたもの」とのこと。
★『こんとんの居場所』の奇妙な味にハマる人がじわじわ増加。
「中日新聞」(8月6日付)では豊﨑由美さんが「重要なのは一見バカバカしい物語の底の底に横たわっている自我や生命という命題に向ける哲学的な問いだ。笑いながら考えさせられる。山野辺太郎は本当に不思議な小説家だ」という魅力的な評を書かれました。
★『近代日本美術展史』がその独自の研究で評価を得ています。
「週刊読書人」(8月11日付)で「本書は見方によっては展覧会の(失われた)黄金時代の記録とも言える。それを支えた男性たち(見事に男性しか登場しない)が退場した後、どんな「美術展史」が続いていくのか。転換期の現在だからこそ書かれねばならなかった一冊なのだろう」との評が児島薫さん(実践女子大学教授)から。
★『幽霊綺譚 ドイツ・ロマン派幻想短篇集』は読書達人の間でかなりの評判。
「産経新聞」書評欄(8月20日付)では、「まずは200年の時を超え、ディオダディ荘え楽しまれた怪談集が本邦に再生したことを寿ぎたい」(平戸懐古さん・翻訳家)
★『ウィトゲンシュタインの愛人』が雑誌「リンネ」10月号「旅のお供の読書案内」に。
「日常のたわいない話から美術や映画、哲学まで、まるで知的な連想ゲームのよう。その中にふと浮かんでくる家族との思い出が哀しくも暖かい」(編集部Fさん)
★〈奇想天外の本棚〉『フランケンシュタインの工場』の書評が「図書新聞」(8月5日付)に。
「1975年頃に予想した地球の未来像を知ることができて面白い」「「四十八年前に書かれたとはとても信じられない」(品川暁子さん・ライター)
★『そして私たちの物語は世界の物語の一部となる』の書評が同じく「図書新聞」(9月2日付)と「週刊読書人」(9月22日付)に。
「一つ一つ丁寧に紡がれた言葉を拾いながら、世界のどこかに暮らすあなたのことを思い、日本語という自分たちの言葉で自分たちの物語を語り、あなたとつながる選択肢が私たちにもあることに気づかせてくれる」(図書新聞・大工原彩さん・翻訳家)
「こんなに頁のすすむ本は久しぶりだった」「そして何よりそれが一地域の記憶ではなく世界の記録となったことは文字通り歴史的快挙である。なぜなら彼女たちの物語は、もはや世界の物語となったのだから」(週刊読書人・山本伸さん・東海学園大学教授)
★〈奇想天外の本棚〉『五つの箱の死』の書評が「図書新聞」(9月9日付)に。
「ミステリ好きのなかには「ついに」と膝を打たれる方もおられるだろう」「カーの脂の乗りきった時代に書かれた『五つの箱の死』は、さほど高い評価を得ていなかった。あまりにも有名な代表作『孔雀の羽根』『ユダの窓』に発表年がはさまれていること、トリックがフェアでないと評されていたことが、そのおもな理由だという。山口氏によれば、今回はカーの「名誉回復」のための試み。読みやすくなった新訳で本作の真価を問う。
★『ウアイヌコㇿ コタン アカㇻ ウポポイのことばと歴史』の書評が地元「北海道新聞」(9月10日付)に。
「本書はウポポイについての絶好のガイドブックであると同時に、その黎明期を内側から記録した歴史史料でもある。将来にわたって何度も読み返されることで本書の意義はさらに深まっていくだろう」(山崎幸治さん・北海道大学教授)
★『暗い庭』の書評が「図書新聞」(9月16日付)に。
「およそ百年前の短篇集だが、むしろだからこそ、読むたびに新たな発見があるだろう。枯葉の如き長い囁き声に耳を傾けよう。打ち捨てられた古い庭、暗い庭の囁きに!」(中野善夫さん・翻訳家)
宝塚少女歌劇で活躍し、戦中名画『無法松の一生』のヒロイン役で日本中を魅了するも、32歳で広島の原爆に斃れた劇的な人生。大林宣彦、井上ひさし作品のモデルとなった伝説の女優・園井恵子の初の評伝。
カズオ・イシグロ絶賛「今年のベスト・ブック」! 〈文学界のロック・スター〉〈ホラー・プリンセス〉による、12篇のゴシカルな恐怖の祭典がついに開幕!!!【2021年度国際ブッカー賞最終候補作】

いいんだよ、これで。なくなったんじゃなくて、変化しただけ――。 文藝賞受賞作『いつか深い穴に落ちるまで』(2018)、『孤島の飛来人』(2022)に続く、現代文学の異才による、二つの変身譚。

明治初期から《モナ・リザ》来日まで100年に及ぶ美術展の歴史を、日本ならではの特徴である新聞社や百貨店の参画・連携にも注目しながら、知られざるエピソードを交えてたどる通史。年表、索引を付す。
『フランケンシュタイン』を生んだ、そのきっかけの書----いわゆる「ディオダティ荘の怪奇談義」で震撼ならしめたのが本書である。E.T.A.ホフマンにも影響を与えた伝説の恐怖小説アンソロジー!
地上最後の一人の女性が、海辺の家で暮らしながら、終末世界の「非日常的な日常」をタイプライターで書き綴る......息をのむほど美しい〈アメリカ実験小説の最高到達点〉。推薦=柴田元幸・若島正。
〈奇想天外の本棚〉『フランケンシュタインの工場』(エドワード・D・ホック 著/宮澤洋司 訳/山口雅也 製作総指揮)
『フランケンシュタイン』+『そして誰もいなくなった』!? 現代ミステリの旗手ホックが特異な舞台設定で描くSFミステリ〈コンピュータ検察局シリーズ〉の最終作。本邦初訳。
一九四四年四月、日本軍がやってきた...村の女性と日本軍士官との短いロマンスを描いた「四月の桜」......インド、ヒマラヤ山脈の辺境から届いた現代の寓話。本邦初のインド北東部女性作家アンソロジー。
深夜一時、女性に請われるまま、部屋に足を踏み入れたサンダース医師が目にしたのは、食卓を囲んで座る物いわぬ四人の人間であった。不可能犯罪の巨匠の手練れの技が冴える、本格ミステリ黄金時代の傑作。
2020年7月に開業した「民族共生象徴空間」(愛称ウポポイ)。アイヌの歴史と文化を展示と体験からどう伝えるか。中心施設の国立アイヌ民族博物館が豊富な写真でわかりやすく伝える、初の公式本。
マリオ・プラーツが『肉体と死と悪魔』において言及した数少ないスペイン作家バリェ=インクラン。W・B・イェイツやガルシア=ロルカを想起させる作品など、この世ならぬ場所へと誘う、17の短篇小説。